||天下第一武勇の士 源義家||
(1039〜1106年)
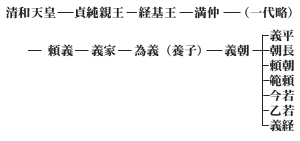
「同じき源氏ともうせども、八幡太郎はおそろしや」と「梁塵秘抄」にもその武勇をうたわれたのが、源頼朝の祖父義家です。7歳の時に石清水八幡宮で元服して、八幡太郎と名のりました。前九年の役には、父頼義にしたがってたたかいました。衣川館にたてこもる安倍貞任に、「衣のたてはほころびにけり」とうたいかけたところ「年をへし糸のみだれの苦しさに」とこたえたので、貞任の心ばえにかんじて、義家が攻撃をやめさせた話は有名です。勇ましい武将であった義家は、同時に学問への理解も深く、思いやり深い人物でもありました。後に五年の役がおこった時、苦戦する義家のために、朝廷に仕えていた弟の義光が地位をなげうって戦場にかけつけた、という話も伝わります。
武士といえば源氏、なかでも義家とその家来たちをさすほどに源氏の勢いは高まり、戦の神様にもたとえられた義家ですが、朝廷はその働きをことごとく無視しました。やむをえず、義家は手柄のあった家来に、自分の土地や財産を与えました。こうして、義家の情けに感動した東国武士たちと義家の絆は深まり、源氏は東国一帯に広く勢力を広めることになるのです。
義家が功績を認められたのは、後三年の役ののち15年もたってからでした。そればかりか、弟義綱との対立や子義親の悪行に悩まされ、苦しい立場の中で終えた一生でした。